「今、株価は一時的に高いだけ?それとも、歴史的な大バブルなの?」
個別株や短期的なニュースに惑わされず、市場全体が長期的に見てどの水準にあるかを判断することは、賢明な資産形成に不可欠です。
この記事では、投資の神様ウォーレン・バフェットも重視する「バフェット指数」や、ノーベル賞経済学者の提唱した「CAPEレシオ」など、市場の長期的な健全性や割安度を測る強力な指標をわかりやすく解説します!
💡 長期指標の重要性:なぜ「全体感」が必要なのか?
PERやPBRといった指標は現在の収益や資産を基準とするため、短期的な景気変動の影響を受けやすい側面があります。
一方、今回ご紹介する指標は、市場の時価総額と経済の規模を比較したり、過去の平均利益で株価を評価したりすることで、一時的なノイズを除去し、市場の真の過熱感や割安度を教えてくれます。
📊 市場の長期的な割安度・過熱感を測る主要指標一覧
1. バフェット指数 (Buffett Indicator)
| 指標名 | 意味 |
|---|---|
| バフェット指数 | 市場の時価総額を国の経済規模(名目GDP)で割った比率。 |
【市場全体での使い方】
- 計算:国内株式市場の時価総額 ÷ 名目GDP
- 判断の目安:
- 100%程度 → 適正水準(株価は経済成長に見合った水準)
- 120%以上 → 過熱水準・割高(経済の実態以上に株価が買われている)
- 80%以下 → 割安水準(株価が経済の実態に対して安く放置されている)
米国市場の参考リンク:MacroMicro
💡 初心者向けポイント
ウォーレン・バフェットが「どの指標よりも、これは市場が割高か割安かを判断する最良の尺度だ」と述べたことで有名です。「国の経済力に対して、株の価値が上がりすぎていないか」を測る物差しだと考えるとわかりやすいでしょう。
詳しい解説はこちら↓↓↓
2. CAPEレシオ (Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio)
| 指標名 | 意味 |
|---|---|
| CAPEレシオ (シラーPER) | 株価を、過去10年間(インフレ調整済み)の平均利益で割った比率。 |
【市場全体での使い方】
- 計算:現在の株価 ÷ 過去10年の平均EPS(1株あたり利益)
- 判断の目安:
- 長期的な平均値(例:米国市場なら約16倍)と比較します。
- 平均値より高い → 割高・過熱感あり
- 平均値より低い → 割安感あり
米国市場のCAPEレシオはこちら
💡 初心者向けポイント
景気が良い時は企業の利益(EPS)が一時的に膨らみ、PERが低く見えがちです。CAPEレシオは10年間の平均利益を使うことで、景気循環による利益のブレを平準化し、「本当の収益力」に対して株価がどう評価されているかを見抜くことができます。ノーベル経済学賞受賞者のロバート・シラー教授が提唱したため、「シラーPER」とも呼ばれます。
詳しい解説はこちら↓↓↓
3. トビンQ (Tobin’s Q)
| 指標名 | 意味 |
|---|---|
| トビンQ | 市場の時価総額を、企業の資産の再調達コストで割った比率。 |
【市場全体での使い方】
- 計算:市場価値 ÷ 資本の再調達費用
- 判断の目安:
- 1.0より大きい → 割高(市場価値が、同じものを今作り直す費用より高い)
- 1.0より小さい → 割安(市場価値が、同じものを今作り直す費用より安い)
米国市場の参考リンク:YCHART
💡 初心者向けポイント
「今、この会社(または市場全体)をゼロから作り直す費用と比べて、市場で売買されている価格は妥当か?」を測る指標です。1.0を超える状態は、市場が企業の資産に対して過度なプレミアム(上乗せ評価)を与えていることを示します。
詳しい解説はこちら↓↓↓
🎯 まとめ:長期指標を投資戦略に活かす方法
これらの長期指標は、短期的な売買タイミングを計るよりも、「今、資産の大半を株式に振り向けるべきか?」という大きな資産配分の判断に役立ちます。
- 指標がすべて過熱水準のとき:株式の比率を減らし、キャッシュや債券などの安全資産を厚くする。
- 指標がすべて割安水準のとき:積極的に株式の比率を高めるチャンスと捉える。
これらの大局的な指標を定期的にチェックして、感情に流されることなく、冷静に長期的な投資戦略を立てていきましょう!
✅ 次のアクション
米国や日本の現在のバフェット指数やCAPEレシオが何%で推移しているか、最新のニュースや経済サイトで調べてみましょう。長期的な平均値と比較することで、今の市場の立ち位置がよりクリアに見えてくるはずです。
その他
投資、経済の基礎知識
投資や経済関連の基礎知識などの記事はこちらにあります。

投資に関する豆知識

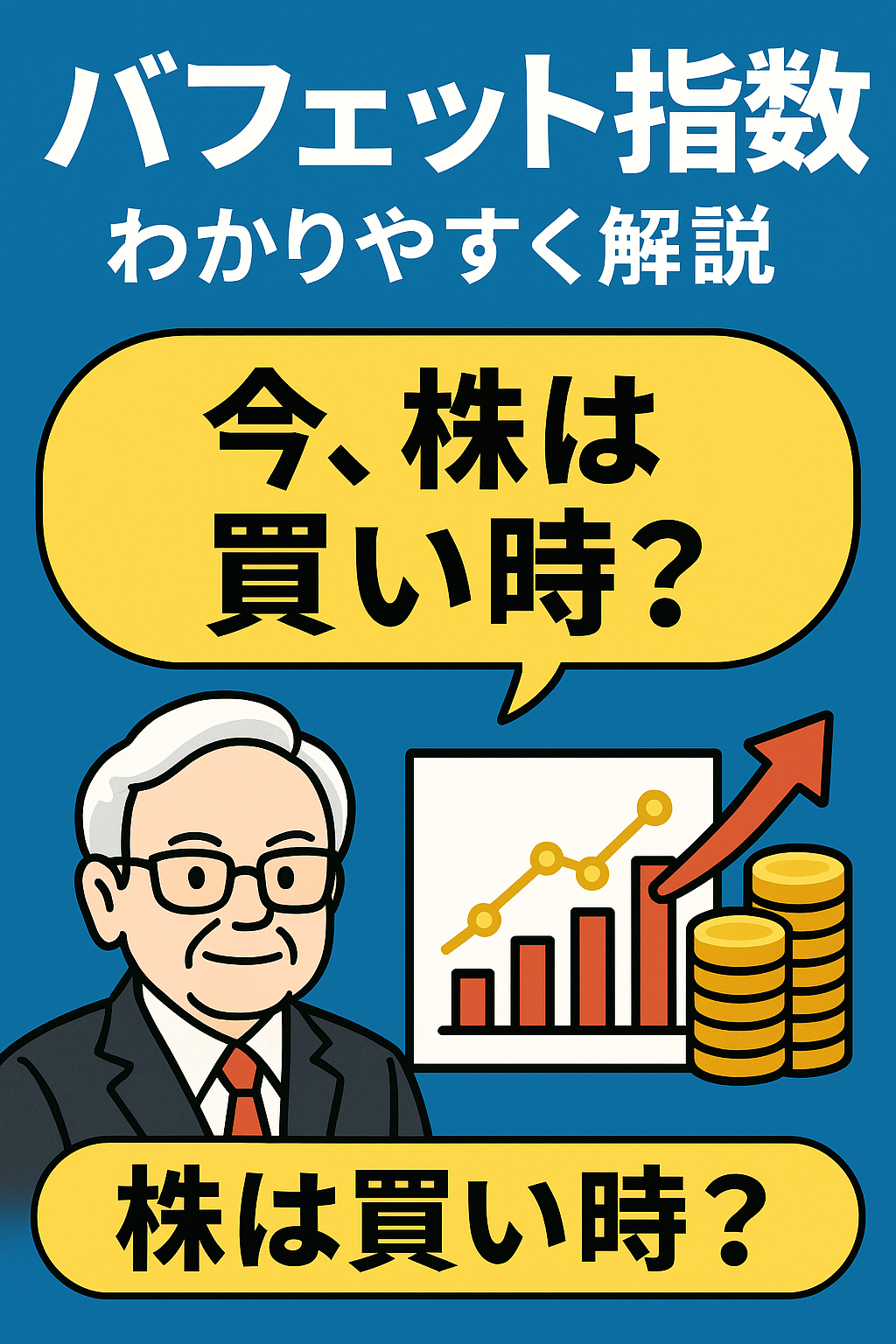
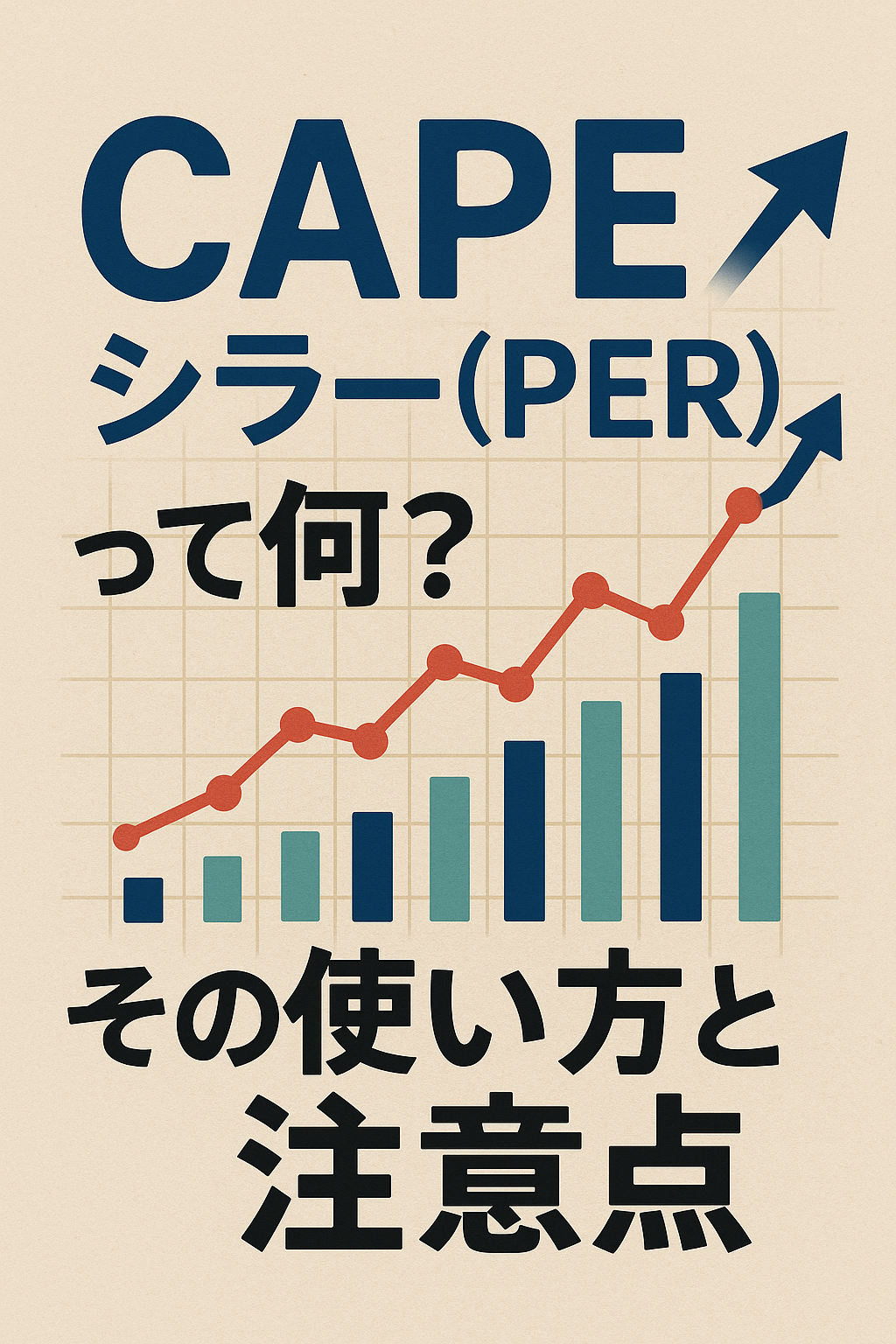
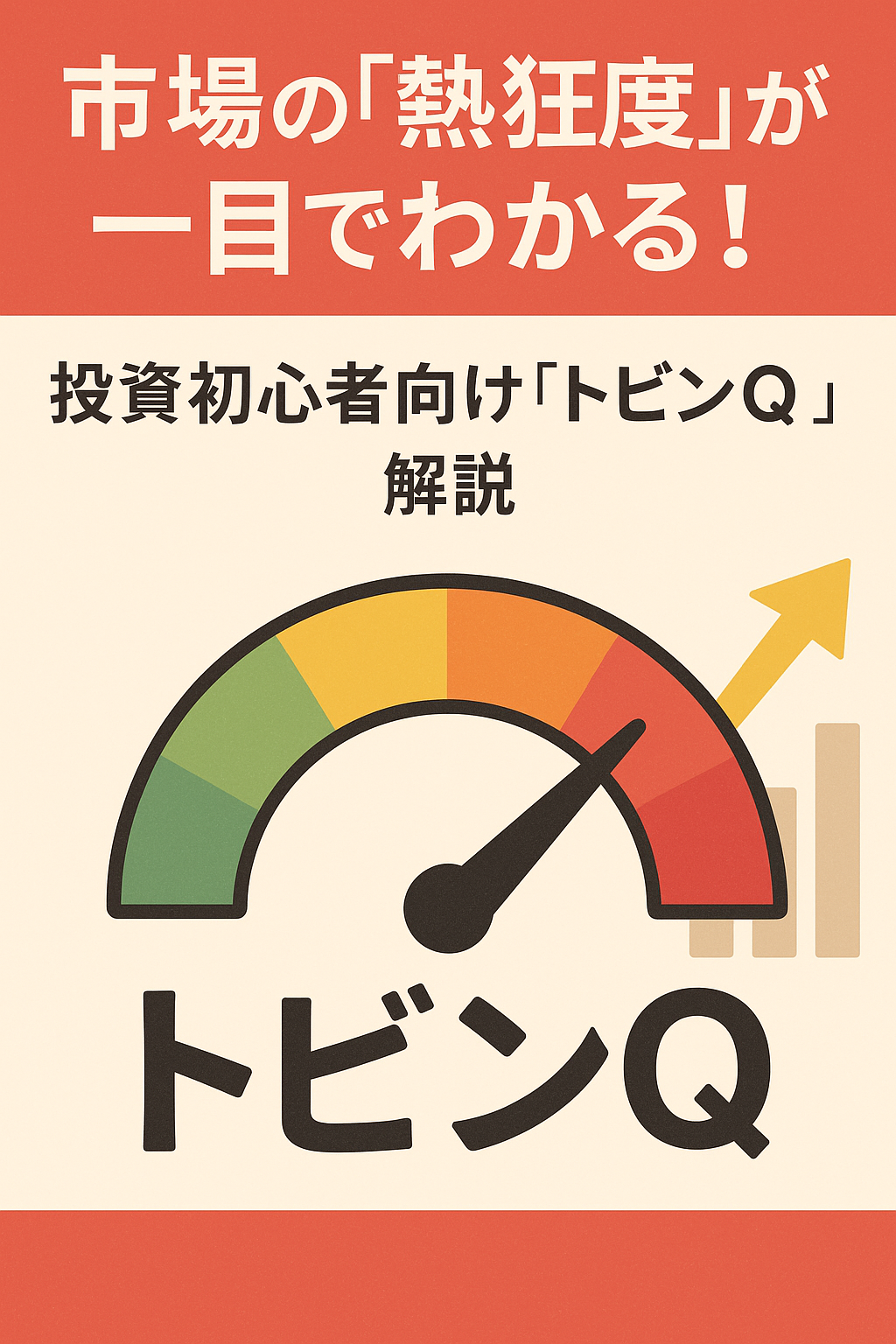


コメント