「マネーストック」や「マネタリーベース」という言葉を知ると、
経済ニュースの内容が少しわかるようになりますよね。
でも本当の理解はここから!
これらの“お金の量”をベースに、「どうやってお金が増えるのか」「なぜ景気が動くのか」を知ると、投資判断の視野が一気に広がります。
今回は、マネーストックを学んだ次に押さえておきたい金融・経済の基本概念を、わかりやすく紹介します。
🏦ステップ①:マネーの量を理解しよう
■マネーストック(M1, M2, M3)
経済全体で実際に出回っているお金の量。
私たちが銀行口座に持っている預金なども含まれます。
👉 例:「お金が回っていない」と言われるときは、このマネーストックの伸びが鈍いことが多いです。
詳しい解説はこちら↓↓↓
■マネタリーベース
日本銀行(日銀)が供給している「基礎マネー」。
紙幣・硬貨+銀行の当座預金で構成されます。
👉 日銀が国債を買い入れることで、この量が増えます。
詳しい解説はこちら↓↓↓
💱ステップ②:お金が「増える」仕組みを知ろう
■信用創造(Credit Creation)
銀行が預金をもとに貸出を行うことで、世の中のお金が増える仕組みです。
たとえば100万円の預金が、貸出と再預金を繰り返すことで数倍に膨らみます。
👉 銀行は「お金を増やす装置」とも言えます。
詳しい解説はこちら↓↓↓
■マネーマルチプライヤー(貸出倍率)
マネーストックがマネタリーベースの何倍になっているかを示す数値です。
この数値が高いほど、銀行の貸出が活発だといえます。
詳しい解説はこちら↓↓↓
💹ステップ③:お金の動きを左右する「金利」と「政策」
■金利(政策金利・短期金利・長期金利)
お金の“レンタル料”のようなもの。
金利が下がると借りやすくなり、景気が刺激されます。
金利が上がると逆にお金の流れが鈍ります。
詳しい解説はこちら↓↓↓
■金融政策(Monetary Policy)
中央銀行が景気をコントロールするために金利やマネタリーベースを調整する政策。
代表的な手法:
- 量的緩和(QE)
- マイナス金利政策
- イールドカーブ・コントロール(YCC)
👉 株式市場はこの政策に非常に敏感に反応します。
詳しい解説はこちら↓↓↓
📈ステップ④:経済全体の「結果」を見る指標
■インフレ・デフレ(物価上昇率)
マネー量と物価の関係を理解すると、「なぜお金を増やしても物価が上がらないのか?」が見えてきます。
詳しい解説はこちら↓↓↓
■名目GDPと実質GDP
- 名目GDP:物価変動を含めた経済の規模
- 実質GDP:物価変動を除いた“実力”の経済成長
投資家にとっては「実質GDP」がより重要です。
詳しい解説はこちら↓↓↓
🔍ステップ⑤:応用編で全体像をつかもう
■貨幣の流通速度(Velocity of Money)
お金がどれくらい速く回っているかを表す指標。
同じマネーストックでも、流通が早ければ景気は活発になります。
👉 有名な式「MV=PY(貨幣数量説)」の“V”の部分です。
詳しい解説はこちら↓↓↓
■中央銀行のバランスシート
マネタリーベースの裏側には日銀の資産(主に国債)があります。
国債を買い入れることでお金を供給する=マネタリーベース拡大です。
詳しい解説はこちら↓↓↓
■銀行準備制度(Required Reserves)
銀行が預金の一部を日銀に預ける仕組み。
信用創造のブレーキになる制度です。
詳しい解説はこちら↓↓↓
💡まとめ:金融知識の学び方ステップ
| 段階 | 学ぶテーマ | ポイント |
|---|---|---|
| 基礎 | マネタリーベース/マネーストック | お金の量を理解 |
| 中級 | 信用創造・マルチプライヤー・金利 | お金が増える仕組みを理解 |
| 上級 | 金融政策・GDP・物価 | 経済全体の動きを把握 |
| 応用 | 流通速度・日銀バランスシート | 市場・政策を分析できる段階へ |
✨さいごに
投資をするうえで、チャートや企業分析ももちろん大事ですが、
「そもそもお金とは何か?」を理解しておくことは、
長期的に投資判断を間違えないための“基礎体力”になります。
マネーストックの次は、ぜひ「信用創造」と「金融政策」を学んでみてください。
経済ニュースがストーリーとして見えるようになりますよ。
その他
投資、経済の基礎知識
投資や経済関連の基礎知識などの記事はこちらにあります。

投資に関する豆知識

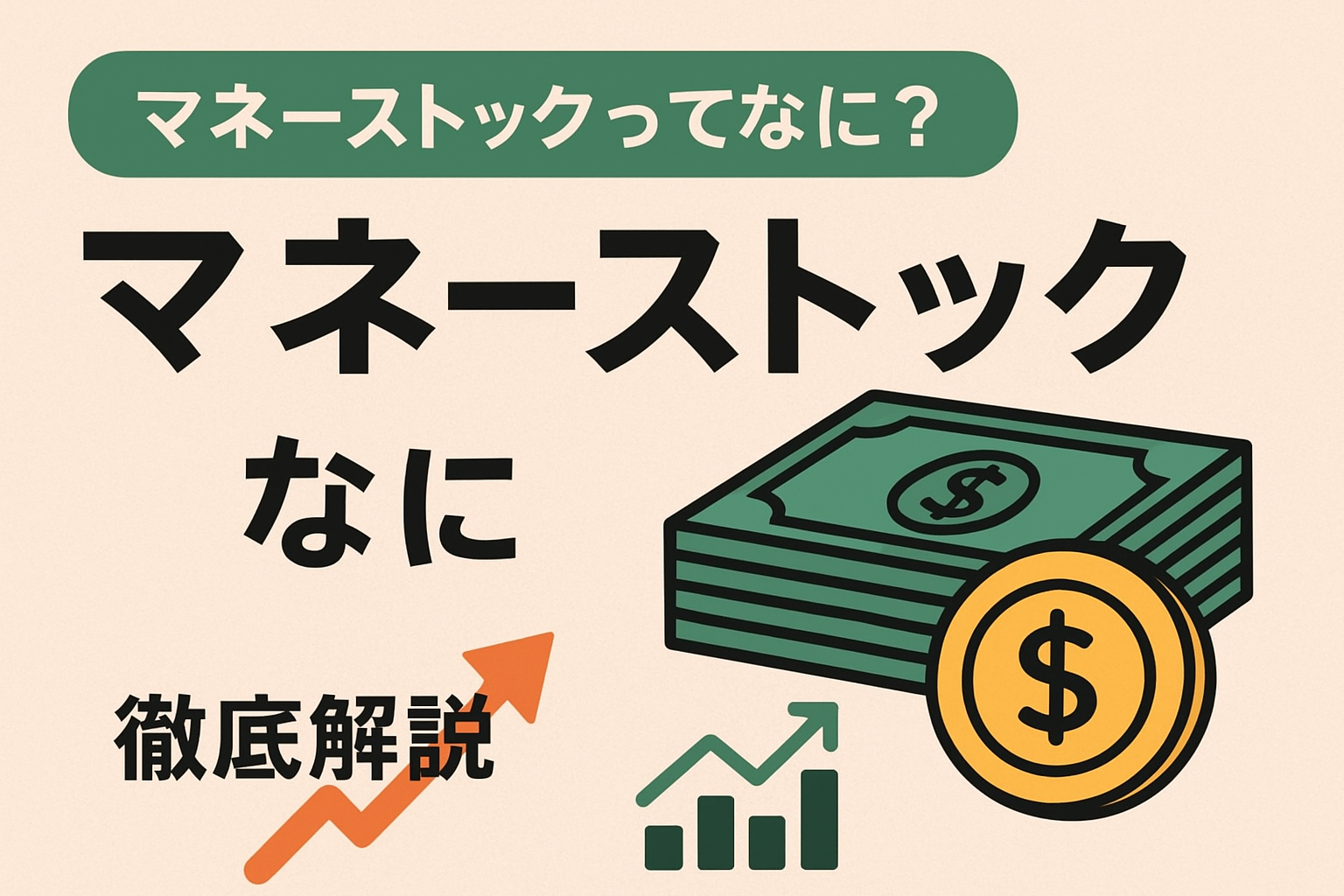





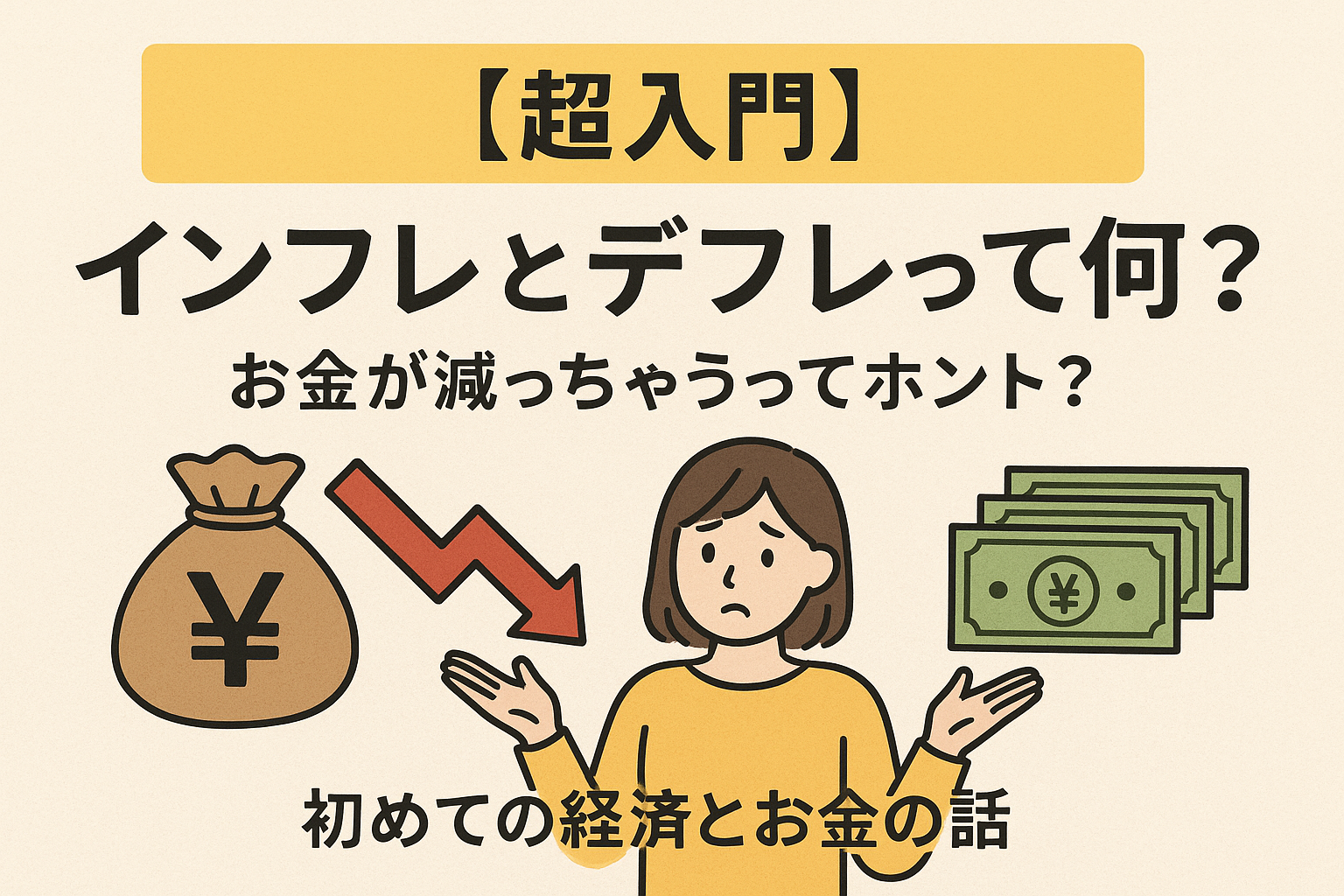

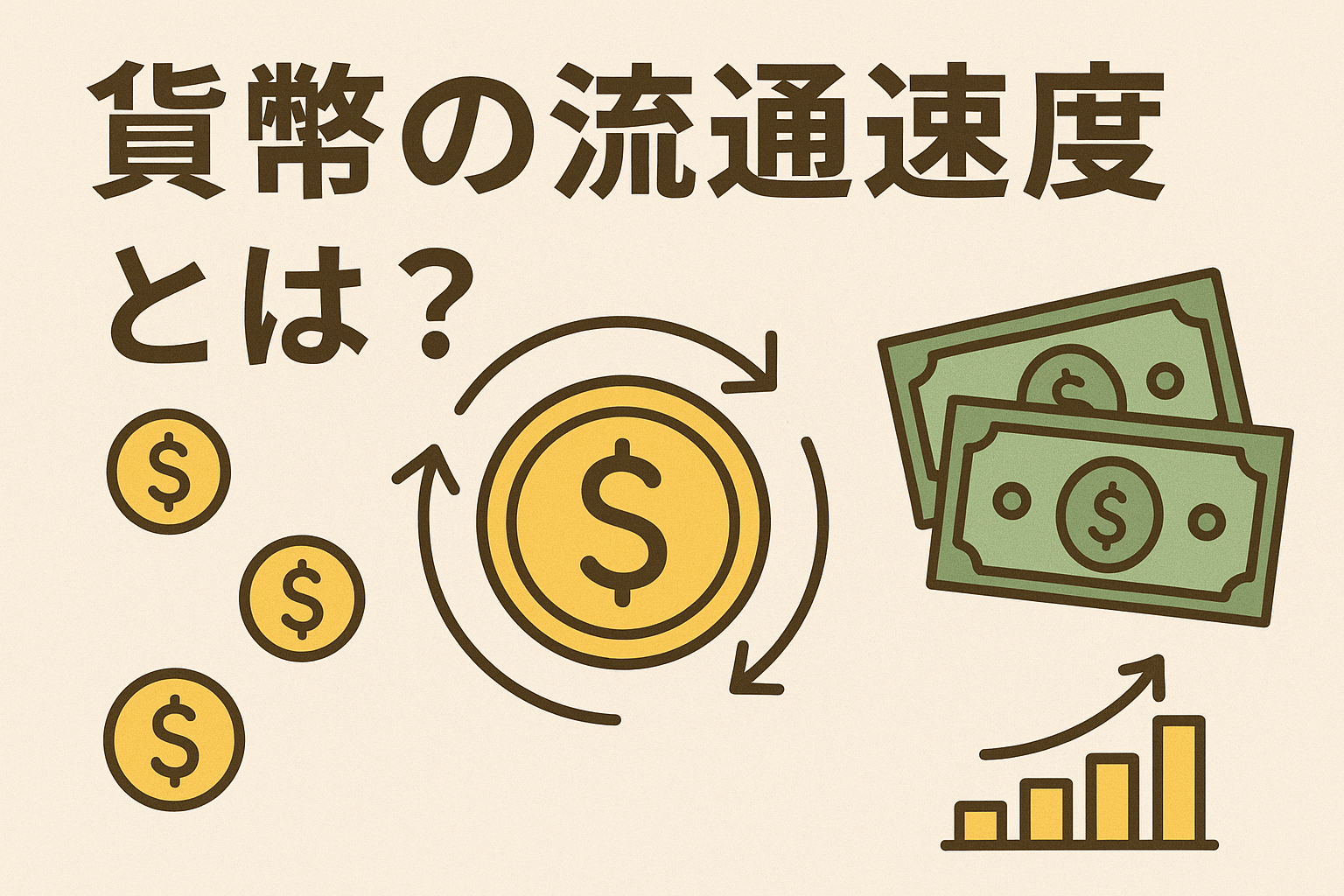




コメント